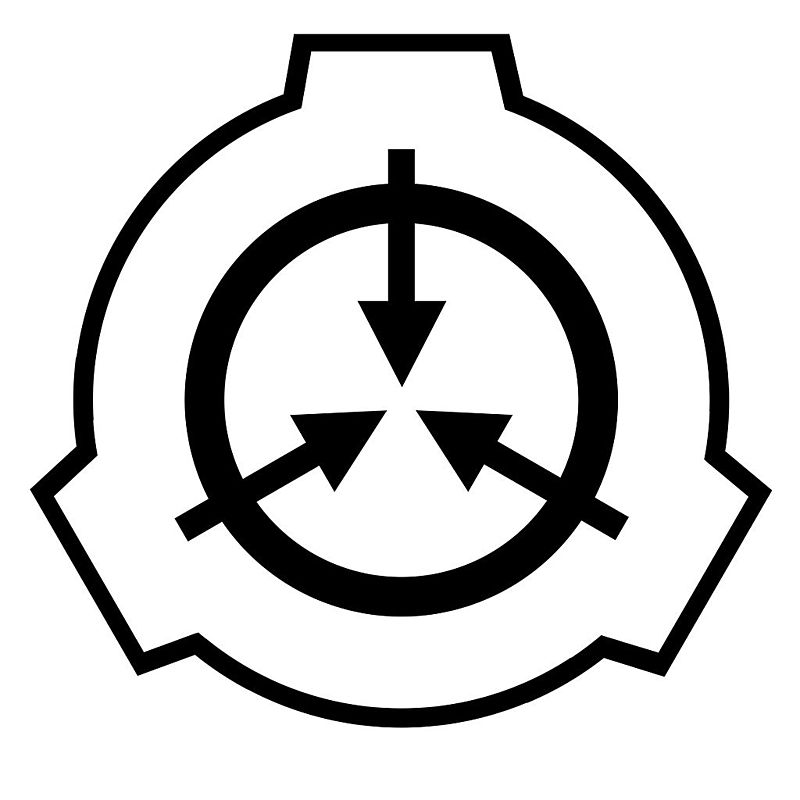禅とは何か?
禅。
日本人の多くが知っているようで
実はよく知っていないこの言葉。
そんな禅の精神を知る上で、
とてつもなく有意義な一冊を
つい先日読んで感銘を受けたのでご紹介したい。
明治生まれの禅僧、関大徹(敬称略)の著書
「食えなんだら食うな」だ。
この本が最初に出版されたのは昭和50年(1975年)のことで、
著者の関大徹も既に1985年に他界されている※のだが、
この本の熱烈なファンである著述家の執行草舟らの尽力によって
2019年に40年の時を超えて復刊したという経緯を持つ一冊である。
(※明治期以降曹洞宗人物誌(六) - 愛知学院大学機関リポジトリ より)
著者の関大徹は明治36年に福井県で生まれ、
十三歳で曹洞宗の寺院に入ると
残りの人生全てを禅の道に捧げ
生涯菜食、女犯を貫いた生粋の禅僧だ。
そんな著者の言葉は
一切の虚飾や遠慮のない実直なもので、
執行草舟氏が帯に「俺は、この本がしぬほど好きなんだ!」
とデカデカと書いているのも頷けるパワーと鋭さに満ちている。
禅の思想や死生観についてはもちろんのこと、
結婚や教育、お布施の是非、お寺とお金の話など
「こんなことまで語っちゃうの!?」と
驚くような話も含まれる本書だが、
本日はその中から説く私にとって興味深かった
5つほどのテーマにフォーカスしつつ、
私が本書から得た知見や驚きを皆様に共有してみたいと思う。
食えなんだら食うな
食えなんだら食うな。
なんだか深いことを言っているようにも聞こえるし、
当たり前のことを言っているようにも聞こえる
なんとも不思議な言葉ではないだろうか。
本書のタイトルにもなっているこのフレーズの意味するところが
最も明確に現れているのが本書の冒頭に収められている
晩年の関大徹がある時
貧乏寺の跡取りだという青年僧から
禅僧の副業の良し悪しを尋ねられた時に
「禅僧は兼業などすべきではない」
立場から返答したエピソードだろう。
それでいいではないか。食えなければ食わねば宜しい。
いったい、高祖禅師(道元)いらい、お寺へ入ったら食える保証など、
どこにもあったためしはない。
お寺で食えるというのが間違っているのであって、お寺は食う処ではない。
もったいないことに、自分の修行に夢中になっているために、
お百姓さんのように一粒の米も生産することができないから、
行乞に出て、すみませんといって、一握りの米をタダで頂戴して、生き永らえさしてもらっている。
自分は僧侶として好きなことをやっているのだから、
一握りの米も頂けなくなったら、誰を恨むでもない。
そのときは、心静かに飢え死にすればいい。
高祖いらい、みんなその覚悟でこられたからこそ、
こんにちの禅門があり、禅僧といわれる人は、その祖風をしたって仏門に入ったはずである。
なんという澄明な境地だろう。
食えなければ甘んじて死ねば良い。
自分の生死にすら執着を持たないという、
禅僧の鑑のような答えだと思う。
だけど、私は最初にこの言葉を読んだ時、
感銘を受けつつも同時に少し引っかかる部分もあった。
なぜなら私を含め世の一般人の多くは
そこまですっぱりとは自分の生死を割り切れないものだし、
なにより養う家族がいれば
「食えなんだら食うな」などとは
とても言っていられないことは明白だからだ。
案の定、質問をした青年僧もその点が引っかかったらしく、
この答えに対して完全には納得がいっていない様子だったらしい。
そして、はそんな青年僧の様子を踏まえて
関大徹はさらに次の様に言葉を続けている。
なんということだ。
どの先得が、そのようなことを仰せられた。
禅僧が禅僧としての修行を全うするために、
妻の協力が必要であると説かれたか。
本来、禅をやるものには、妻子は養えぬのである。仏道修行が女性を近づけぬのは、
単なる性欲の問題だけでなく、
そういう普通一般の日常という
荷物が、重すぎるという理由もあると私は思う。
禅だけではない。
自分で自分の好きな道に熱中するものは、
まず妻子というものを斥けてかかったほうが無難であろう。好きなこともやりたい、妻子も食わせねばならぬというのは、
それこそ二足のワラジであり、どだいムシの良すぎる注文である。
ここまで読んでハッとした。
これは不邪淫の戒を厳格に守っている
禅僧としての立場からの言葉だったのだ。
つまり禅の道とは
子育てのような一大事の片手間に極められるほど
生易しいものでは無く、ゆえに
養う家族が云々という言い訳が
そもそも成り立たないという事を言っているのだ。
わが身一つ、いつ野垂れ死にしても
満足という覚悟でなければ、
それは、脇目もふらず自分の選んだ道を歩いているとはいえず、
裏返していえば、妻子を養うということは、
それほど値打ちがあるということになる。
すくなくとも、男たるもの、
男の一途さを放棄せねば、妻はめとれぬ。子は設けられぬ。
なんのことはない。
妻子の為に死ぬこともままならぬのである。
まさに憂き世である。悪いことはいわない。
まだ、妻帯の決心のつかぬ男性諸君は、
この事の重大さに思いを馳せてほしい。家庭という重荷を背負うか、
わが身一つの身軽さでゆくか、
選択できる間に選択しておくことだ。
今よりもなお、結婚して子供を育てることが当たり前だった時代に
あえて結婚も子育てもせず一つの道を究めることに
人生を捧げる道を選んだその覚悟はいかほどのものだったろうか。
そして、結婚して重荷を背負うか、
結婚せず身軽に自分のやりたいことをやり通すか
まだ結婚していない男は
今のうちに選んでおけと言う結びの言葉。
私などはまさにそういう立場にあるわけだが、
個人的にも仕事人間で最終的に
家庭を維持できなかった父親の事を知っているだけに
この言葉は一層ずしりと重く腹の底に響いた。
無報酬ほど大きな儲けはない
人間の心理には自分が誰かにしてあげたことを過大に捉え、
逆に自分が誰かからしてもらったことは
過少に認識してしまうバイアスがある。
そして一度誰かに「親切にしてやった」と思い込むと
その人が自分になんらかの「お返し」を
するのが当然だと無意識のうちに期待し、
それが満たされない場合には
相手のことを恩知らずだと言って怒ったり恨んだりする。
このような経験をしたことがあるのは
きっと私だけではないと思うが、
「無報酬ほど大きな儲けはない」と題された
本書のある章において関大徹は
そんな私たちの中に潜むさもしい心を、
お寺に寄付を受けてもおおげさに感謝しないようにしているという
自身の心がけを引き合いに出して次のような言葉で指弾している。
そうではないか。
寄付というのは、まったく無償の行為である。
無償の行為であってこそ、それは「徳」として完成する。人間、なかなか徳を積めるものではない。
自分のためなら、死にもの狂いで働くこともできるが、
他人様や仏様のために、一切を投げうつという真似は、
天地がひっくりかえってもできないのが普通であろう。P78より
「徳」は無私でなければならない。
無報酬でなければならない。
そうしたなかで、おおやけごとやお寺のことに
寄進できるというのは、せめてもの徳を
積ませていただく有難い機会であり、
無私な心境に自分を高めることができるのである。
P79より
善行は「してやっている」のではなく
「させていただいている」。
ちょっとした発想の転換だけど
こう考えてみると世界の見え方が
大きく変わって来ないだろうか。
少なくとも私は本書を読んで
この考え方を常に胸に置くようになってから
対人関係のストレスの何割かが減少し、
また自分が人に親切をするときにも
あくまでも自分が徳を積むためということで
以前より気負わず自然にできるようになったとも思う。
また、この下りを読んで思い出したことだが、
私が昔読んだ『反応しない練習』という
これまた僧侶(こちらは元だったが)の人が書いた本の中に
人間の苦しみの根本が「期待する」という
心理にあるといった事が書かれていた。
これは全く言い得て妙で、
思えば今まで必要以上の期待を抱くことで
実に多くの無駄なストレスを抱え込んできたように思う。
「親切はさせていただくもの」
「他人には最初から期待しない」
どちらも書籍を通じてであったこの二つの考えは
私にとってなんとも頼り甲斐のある言葉になった。
ガキは大いに叩いてやれ P108
教師が子供の頭を小突いただけでも
大騒ぎになる現代の感覚からすると
これはかなりハラハラさせられる主張ではないだろうか。
多くの人は、いきなりこのようなことを説かれても
積極的な体罰容認派でもない限り
「まぁ書き手が昭和どころか明治生まれの方だから
その辺りの感覚が今と違うのは当然だよな」
程度にしか思えないのではないかと思う。
(事実、私も最初にこの一文を目にした時にはそう思った)
しかし、本書で関大徹が語る
この主張の根拠となったある体験談を読んだ後では、
単なる時代感覚の違いという理由だけで
この意見を退けていいようには
少なくとも私には思えなくなった。
その体験談というのは、
本書の執筆の四十年ほどの前に
関大徹が当時在籍していた
富山のお寺の運動場で目にした
子供のある行動にまつわる話だ。
そのお寺は幼稚園の役割も果たしていて、
境内には子供が遊ぶための運動場があったのだが、
ある時そこで遊んでいた子供たちの輪の中に
近くの樹の上から雀の子供が落ちてきた。
日頃から命の大切さを
子供たちに教えていた関大徹は
自分の教育が子供たちに伝わっているかを確認する
良い機会だとして、この事態に子供たちが
どう反応するのかを遠くから見守っていたのだが、
しかし最初はこわごわ見ていた子供たちの一人が
やがて雀に手を伸ばして行った行動は、
関大徹の期待に反して
無力な雀の子を捻りつぶそうとするものだった。
それを見た関大徹は
咄嗟にその子供の元へ飛んでいき、
子供の首根っこを捕まえてしまう。
柔剣道の心得のある私は、
「急所」を外していたけれども、
かなり、きつくつまみ上げたようである。
子供は、悲鳴を上げ、手の雀を放した。
私は、しかし、許さなかった。
子供は、身をもがいて苦しんだ。
「どうだ、痛いか」
「痛い」
私は、やっと、手をゆるめた。
「雀は、もっと痛かったかもしれん。
おまえが痛いように、雀も痛いのだ。わかったか」
「わかった、わかった」
文字で読んでもかなりの「荒療治」だが、
締め上げられた当人にとっては尚更だったようで、
このエピソードの後に書かれている後日談では、
五十歳近い立派な紳士になって関大徹の元を再び訪れた件の「子供」が、
「五十年の人生で、あれほど恐ろしかったことはありません」
と語っていたことが記されている。
五十年も消えないほどの恐怖とは凄いものだが、
確かに人間というのは生存本能からか
楽しかった体験より怖かった体験の方が
尚強烈に記憶に残っていることが多いように思う。
方法についての是非は色々あるだろうが、
やってはいけないことを教えるには
これほど効果的なものはないだろう。
思えば私も子供時代に
料理人である父親から頼まれて引き受けた
仕事道具の片付けの手伝いをするのを忘れて
ゲームに熱中してしまったことで酷く叱られて
泣いても許してもらえずに怖い思いをしたことがあったが、
今思えばあれは、私が将来約束を守れない大人になることを憂慮した父が
あえて厳しく叱ったのではなかったかと思う。
そして、そうだとすれば
あれから20年経った今でもそのことを
はっきり私が覚えているのだから
父の教育方針は決して間違っていなかったということになる。
もちろん、現代で体罰がタブー視されるのには
それだけの理由があって、体罰の名を借りた虐待や
度を過ぎた暴力は絶対に容認されるべきものではないとは思うが、
しかし叱るべき時にちゃんと叱れる大人がいなくなることも
それはそれで世にとって毒なのではないだろうかと
私は本書のこの主張を読んでいくらか思うようになった。
自殺するなんて威張るな P160
本書では、様々な理由から
吉峰寺を頼ってきた人たちの話が語られる。
その顔ぶれは多彩で、ノイローゼの少年や
オートバイ泥棒の高校生、
無理心中を思いとどまった若い母親、
シー・ジャックを計画した過激派の一味など
それぞれの理由は様々だが、
誰もが俗世での苦悩を引きずった人たちばかりだった。
そんな中でもとりわけ
私の心に強く残ったエピソードの一つが、
大学受験の失敗を苦にして自殺を思い立ち
睡眠薬を飲むも死に切れず、
母親に連れられて寺の門を叩いたという
ある受験浪人についての話だ。
寺に住み込み座禅や作務をこなす生活を送るも、
何日経っても一流大学への入学か死かという
二択が脳裏から離れないこの若者の様子を見かねた関大徹は、
ある日の坐禅の最中に警策を加えつつ、次の言葉を投げかけた。
ある朝、暁天の坐禅で、
私は警策をもって歩いていた。座った彼の上体が、ふらふらと動いていた。
私が前に立った。この場合、禅の作法で、合唱して、
警策を受ける姿勢をとらねばならない。私は、手をそえ、
その姿勢をとらせ、
「喝!」
と一撃を加えた。一撃を加えつつ
「自殺するなんて」
と怒鳴った。一撃。
「威張るな」一撃。彼は、
殆ど飛び上がりそうになった。
自殺するなんて、威張るな。
いかにも自殺しそうな人に
何かかける言葉をかけろと言われたら
普通の人はまず選ばないであろう、
ものすごくインパクトのあるフレーズだ。
しかし考えてみればこの言葉ほど
今回のケースの核心をついた言葉もないように思う。
そもそも世の中に生きている人たちを見渡してみれば
一流大学に入っていない人の方が圧倒的大多数であって、
一流大学に入らなければ生きている意味がないというのは、
そうした人たちへの見下しに他ならないし、
同時に自分がそうした大多数の人よりも
であって当然だという慢心と視野狭窄の現れに他ならない。
関大徹はそんな彼の若者特有の心理的盲目を見抜いて
この言葉を選んだのだろう。
そしてその選択は実際に正しかったようで、
本書にはこれを機に彼の憑き物がすっかり落ちたようになり、
それからしばらく寺で過ごした後に
山を降りていったことが記されている。
また、さらに暫くして
若者の母親から届いたという手紙によると、
彼の勉強部屋には「自殺するなんて威張るな」
と書いた紙が貼ってあったそうだ。
ちなみに、ここからは完全な余談だが
私も自殺に関しては少し思うところがある。
今から2年ほど前、私の隣の家に住んでいた
私の弟と同い年の男の子が
20ちょっとの年齢で自殺したという話を
故郷の父親と電話で話しているときに知って、
体の震えが止まらなくなるほどの衝撃を受けたことがあった。
その子は私ではなく弟の友達であり、
私とは弟との繋がりでごく稀に遊ぶ程度だったのだが、
それでも快活で、運動神経が良く、友達も多くて、
勉強もクラスでいつもトップクラスだったという彼が
自殺を選んだなどということはとても信じられない話だった。
私の知る限りではどうやら、
就職活動の失敗が原因だったそうだが、
彼ほど優秀ならば、少し目標を落とせば
いくらでも幸せに生きられる道があったはずだ。
もっとも、なまじ優秀であったからこそ
一度の失敗でポッキリ折れてしまったのかもしれないし
そもそも当事者ではない私に
彼の選択の是非を決める資格はないのだが、
しかし残された彼の家族の悲痛な様子を思うと
彼に対して「自殺するなんて、威張るな」と
行ってあげられる人が側にいればあるいはと
もやもやした思いが募るばかりなのである。
生きるとは死ぬことである
なかには、遠慮深いどころか、
死ぬ話を嫌って、出来損ないの修身みたいな話を、
とくとくとされるかたがおられるのは寒心に堪えない。こういう坊さんにかぎって、
インテリ坊さんを自他ともに認めており、
タレント坊さんなどという妙な種族もおり、
ぼう大な裾野の拡がりを持つマス・メディアを通して、
仏教は死ぬ教えではない、などとほざいてござる。死ぬ教えではなく、生きる教えであるというのである。
冗談ではない。生死一如。
生きるとは死ぬことであり、
死とは生きているもののあかしであるという
仏教の大原則をお忘れか。故意に忘れておられるのなら許す。
しんから御存知なくて、
そんな寝言をいっておられるのなら、
誰か出ていって、袈裟を剥いでやれ。坊主の袈裟を剥ぐとは、
法論に敗れたものへの古来の作法であり、
一たび袈裟を剥がれると、
その人物は永久に追放されるのである。
本書で関大徹は
ある種の仏教者への苦言を呈してもいる。
上記は、仏教の本質である死への言及を避け
当たり障りの無いことばかり話す坊さんや
俗物的なビジネス坊さんへの苦言だが、
生涯独身、菜食主義を通し、
全一筋に生きてきた当人が言うと流石に説得力がある。
また、この話と同じ章には
個人的にこの本で一番
読んでいて痛快だった下りがあるので
そちらも合わせて引用したい。
ちょっとした、小ざかしげな坊さんなら、
ぬけぬけと死の話を持ち出すのは、
なんとしても気が引けてならないのあろう。それば、いうまでもなく、
死者儀礼が坊さんの守備範囲であり、
たんに死者儀礼を行うだけでなく、
それによって、お布施と称する不当な収入を得ているからである。
「不当な」と、あえていう。一般に言われている布施とは「財施」であり、
お坊さんの誦経や法話という
「法施」に対する気持ちのありったけを、
金銭などの財物によって、表現するのである。したがって、それはあくまでも「志」であり、
「志」に意味があり、そのありがたさをいただかねばならない。ところが、不思議なことに「相場」というのものができ、
貧富の差もなにも無視して、
額で決めるのが普通になり、もっとけしからんのは、
一部の都会などでは、葬儀社と坊さんが結託して、
これこれの規模の葬儀にはいくらいくらと
「定価」を示されるというから、呆れるほかはない。P240より
まさかのお坊さんによるお布施批判である。
ここまでぶっちゃけて大丈夫ですかと
読んでいるこちらが不安になるほどのまっすぐな批判だが、
しかし一度でもお寺に葬儀を依頼した経験のある人なら
思わず頷きたくなる内容ではないだろうか。かくいう私も二年ほど前に母の葬儀を経験しており、
またお布施もその流れで支払っていたので
この意見にはかなり共感できる部分があった。しかし、関大徹の舌鋒は
まだまだこの程度では止まらない。多くの日本人がお布施と並んで
疑問を感じているであろう「戒名」に対しては
さらに強烈な批判を加えている。お布施の多寡によって戒名の「格」が変わり、
その格によって生まれる極楽の格も違うというような
大嘘をついて平然としているのは、これは背徳というより犯罪的であり、
せめて犯罪者の汚名を着たくないという良心、ないしは小心さが、
多くのものわかりの良い坊さんをして、仏教は死を説くにあらず、生くる道なり
などという寝言を吐かせるのであろう。P241より
お寺の維持運営という面からも
必ずしも戒名という制度が悪いというわけではないとは思うが、
しかしここで指摘されているように
良い戒名をつけなければ極楽に行けないといった
脅しじみたやり方で金銭を得ようとするお寺があるとすれば
それはやはり本来の道からは外れる行いなのだろう。ただでさえ若者の宗教離れや檀家数の減少が叫ばれる昨今、
お寺が今後も私たちのライフライクルの中に
欠かせざる存在であり続けられるかどうかは
こうした阿漕なやり方ではなく、
仏教寺院が私たちの側から進んで
「志」を収めたくなるような有難い場であることを
正しくアピールできるかどうかに
かかっているのではないかと私はこの一連の下りを読んで思った。おわりに
本書の著者である関大徹は、
妻も持たない、酒も肉も飲まない食べないという
厳しい生き方を最後まで貫いた本当に凄い人だと思う。本書の中には「家事嫌いの女は叩き出せ」なんていう
今の時代のフェミニスト諸氏が聞いたら
泡を吹いて卒倒しそうな主張もあるが、
それらもを含めて新しい視点を知る良い機会となった。禅に興味ある方はもちろん、
生き方に迷いのある多くの人にとって
頼もしい道しるべとなりうる一冊だろう。また、今回紹介した以外にもまだまだ興味深い話や
有難い話が載っているので気になった方はぜひ本書を
ご自身の本棚のレパートリーに加えてみることをおすすめしたい。それでは。