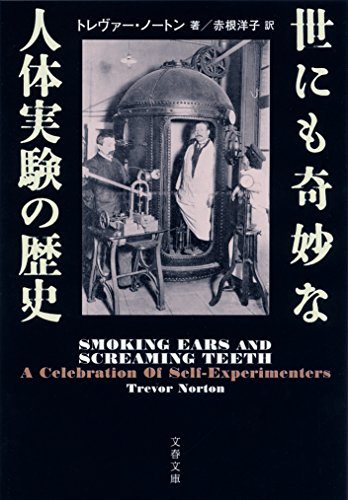はじめに
こんにちは、daimaです。
本日は「寝ながら学べる構造主義」という本をご紹介します。

こちらはフランス現代思想を専門とする
神戸女学院大学名誉教授の内田樹氏が2002年に刊行した書籍であり、
そのタイトルから分かるように構造主義の入門書的な役割を意図して書かれたものです。
マルクス、フロイト、ニーチェら前構造主義の思想家から始まり、
ソシュール、そしてフーコー、バルト、レヴィ=ストロース、ラカンら
「構造主義四銃士」に至る著名思想家たちの代表的な思想を
内田氏独特のシニカルなユーモアとわかりやすい譬え話を交えつつ
初学者にも理解しやすい平易な言葉で解説しています。
「寝ながら学べる構造主義」の(かなりおおざっぱな)要点まとめ
構造主義とはなにか?
・私たちはポスト構造主義の時代を生きている
・構造主義の批判的省察を行う時に使えるツールは構造主義だけであり、私たちはその無限ループの中に閉じ込められている
・構造主義はほんのここ三十年の間に「常識」となった新しい考え方である。
・構造主義とは簡単にいうと「アメリカ人の目から見える景色」と「アフガン人から見える景色は」全く別のものだよ、ということである。
・構造主義以前の例えば1960年代のほとんどのアメリカ人の脳裏には「生身のベトナム人はアメリカのアジア戦略をどう評価しているのだろうか」などといった考えは存在しなかった。
・構造主義以前は、国際的紛争においては、構想の当事者のいずれか一方が「絶対的正義」であるはずだ、という考え方が「常識」だった。
・しかし構造主義では「私たちはつねにある時代、ある地域、ある社会集団に属していて、その条件が私たちのものの味方、感じ方、考え方を根本的な部分で決定している。すなわち、私たちは自分で思っているほど主体的に、自由にものを見ているわけではない。」と考える。
構造主義前史
構造主義の源流その1、マルクス
構造主義のひとつの源流となったのがカール・マルクスである。
マルクスは人間がどの階級に属するかによってものの見え方が変わってくるということ(=階級意識)を指摘した。
そのマルクスは「たいせつなのは自分のありのままであることではなく、
行動によって自分のなりたいと願うものになることである」とした
ヘーゲルの実存主義的人間学から強い影響を受けている。
構造主義の源流その2、フロイト
精神分析学で有名なフロイトもまたマルクスと並んで構造主義の源流のひとつである。
フロイトは人間が実は自分が「どういう風に」思考しているかを知らないで思考していることを指摘した。
フロイトの精神分析から誕生した考えの中に「抑圧」というものがある。
これは人間の自我に備わっている自己防衛のメカニズムであり、
具体的には自分にとって都合の悪い情報や
過去の嫌な体験を思い出す情報に遭遇した時に
これを無意識の内に意識から除外することで
自分自身を守ろうとする働きのことである。
マルクスとフロイトの登場によって
人間が実は自分で思っているほど自由に考えたり、行動したり、欲望しているわけではないことが明らかになった。
構造主義の源流その3、ニーチェ
マルクスとフロイトと同時代を生きたニーチェは
ある時代の社会的感受性や身体感覚のようなものは
「いま」を基準にしては把握できないのだと指摘した。
この考え方はのちにミシェル・フーコーへと受け継がれた。
構造主義の始祖、ソシュール
構造主義の直接の起源とされているのは
スイスの言語学者ソシュールである。
ソシュールは「ことばとはものの名前ではなく、
他と区別するための線引きであって、それは文化によって異なる」という
構造主義にとって非常に重要な知見を示した。
これは、例えば犬という存在が
国によってdogだとかchienだとかhundだとか
様々な呼び名で呼ばれていることからわかるように、
ものと名前の間には本来必然性はなく
人間の都合で恣意的に適当な名前がつけられているだけだとする言語観である。
ソシュールに言わせると、ものは名前をつけられることで
はじめて実在するとのことであり、すなわち命名する前の
「名前を持たないもの」は実在しないということである。
本書では一見直感に反しているように思える
ソシュールのこのアイディアを解説する上で
「devilfish」という単語を挙げている。
これは直訳すると「悪魔の魚」という意味の英語であり
英語圏では主に「エイ」や「タコ」を指す単語だが
日本語にはこれと同様の意味の単語は存在していない。
つまり英語を知らない日本人にとって
「devilfish」と呼ばれるような存在は
どこにも存在していないのも同じであるわけだが、
その同じ日本人が英語を勉強して
devilfishという単語の意味を理解した瞬間に
これまで存在しなかったdevilfishが
その人の頭の中に急に存在するようになる。
また別の例として、英語のsheepと
フランス語のmoutonはどちらも羊を表す単語だが
前者は生きている羊のみを指すのに対し
後者は食肉用に加工された羊肉の意味も含んでいる。
すなわち私たちは言語活動によって
世界を自分たちの文化や風習に都合の良い形に
勝手に切り分けているということだ。
こうしたソシュールの思想は
言語学の枠を飛び越えて後のプラハ学派や未来派、
フッサール現象学などに影響を与え、
本書の本題である構造主義へも繋がっていった。
構造主義四銃士その1。ミシェル・フーコーと系譜学的思考
フーコーはポスト構造主義に分類されるフランスの哲学者である。
歴史は「いま・ここ・私」に向かってはいない
人間の歴史が時代を経るにつれよりよい方向に改良され続けているという考え方(歴史の直線的推移)は幻想である。
フーコーは歴史を一本の線のように捉えて、今自分が立っている場所が最先端だとする人間主義的な進歩史観に異を唱えた。
身体も一個の社会制度である
フーコーによれば人間の身体もまた一個の社会制度に他ならない。
例として江戸時代以前の日本人は「なんば」という同じ方向の手足を同時に出す歩き方をしていたが
明治以降は軍隊の更新をヨーロッパ化するために国策として廃止され、全国の学校で子供のうちに「矯正」されることとなった。
国家は身体を操作する
明治時代には体操が学校教育に取り入れられたがこれは本来軍隊において素人兵を近代戦に適応できるように訓練するためのものだった。
国家主導による体操の普及の狙いは単なる国民の健康増進などではなく、国家にとって都合の良い「操作可能な身体」「従順な身体」を造形することだった。
政治権力が臣民をコントロールしようとするとき、権力は必ず「身体」を標的にする。
内田氏は国家による身体コントロールの例として他にも「三角すわり」を挙げている。
三角すわりをさせられた子供はまず両手を組むために「手遊び」ができず、また首も左右にうまく動かないため注意散漫になりづらく、さらに胸部が強く圧迫される関係で深く呼吸することができず大声も出せなくなる。
要は子供に対し教師の管理の都合から無理な体制を敷いているわけであり、本書ではこのことについて「日本の戦後教育が行ったもっとも陰湿で残酷な身体の政治技術の行使の実例だと思います」と述べている。
構造主義四銃士その2。ロラン・バルトと「零度の記号」
ロラン・バルトの仕事はまとめて「記号学」という名称の元に包括することができる。
「記号」と「象徴」は似ているが別のものである。
例えば裁判所の象徴が天秤であってやかんではないように、象徴はそれが指示するものと何らかの関わりがある必要があるが、記号にはその必要がない。
記号とは、ある社会集団が制度的に取り決めた「しるしと意味の組み合わせ」にすぎない。
記号学とは、私たちの身の回りのどんなものが記号となるのか、それはどんなメッセージをどんなふうに発信し、どんなふうに解読されるのか…を究明する学問である。
バルトの重要な概念のひとつ、「エクリチュール」とは集団的に選択され、実践される「好み」である。
バルトはエクリチュールを誤報とほぼ同じ意味で使っていて、私たちが属する集団や社会的立場に応じて複数の誤報を使い分けているのだと指摘した。例えば「おじさんのエクリチュール」「教師のエクリチュール「ヤクザのエクリチュール」といった具合に。
この考えを発展させると、私たちのことばづかいが私たちの生き方全体をひそかに統御していると考えることができる。
このアイディアをたくみに活用した一例としてフェミニズム批評における言語論があり、
フェミニズム批判理論によれば私たちの社会における「自然な語法」が実は男性的な語法であり、私たちが「自然な語法」で語ることは私たちの社会で男性の性イデオロギーが覇権を握っていることを繰り返し承認し、賛美しているということとイコールになる。
バルトのもう一つの重要な概念として「作者の死」がある。
これは「作者」という近代的な概念がもう「耐用年数」を超えてしまったことを指摘するもので、これは作品の起源に「作者」がいて、それが物語や映像や音楽や文章を「媒介」にして、読者や鑑賞者に「伝達」される、という一方向的な図式を否定するものである。
作者たちは必ずしも「自分たちが何を書いているのか」をはっきり理解しているわけではない。
作品が出来上がる過程には時代的な条件や他の作品への気遣いや競合心など様々なファクターが絡み合っており、作者の意思のみによって作品が成立するわけではない。
バルトは作者は作品を支配できず、読者に解釈を任せるべきだと説いた。
本書中ではこれに対応する例として高い情報拡散性を持つインターネットを挙げており、さらにLinux OSに代表される「オープンソース思想」も挙げている。
構造主義四銃士その3。レヴィ・ストロースと終わりなき贈与
レヴィ・ストロースは「実存は本質に先行する」という言葉で有名なサルトルの実存主義を痛烈に批判した人類学者。
実存主義と構造主義は「主体が与えられた状況の中で決断を通じて自己形成を果たす」という点では同じだが、実存主義が「状況の中で主体は常に政治的に正しい選択を行うべきであり、その政治的正しさはマルクス主義的な歴史認識が保証する」とした点にレヴィ=ストロースは強く異を唱えた。
語彙や概念の豊富さはその集団がどのような対象に深い興味を抱いているかによって決まる。
文明人が歴史や哲学を持たない部族・民族を「野蛮」だと見下すのは自己中心的で傲慢な味方である。
同様に、あらゆる文化、民族がひとつの「ゴール」に向かって進歩し続けているという直線的な歴史観も誤りである。
レヴィ・ストロースは未開社会と文明社会をフィールドワークを通じて研究し、その結果として両者の間に優劣をつけることは無意味であると考えた。
レヴィ・ストロースは「西洋こそが最先端の文化であり、全ての文化が西洋化して進歩するべきだ」というサルトルの主張を、未開部族の人間が別の村の人間を「よそもの」とみる思考パターンと何ら変わらないものだと指摘して当時実存主義の旗手だったサルトルを完膚なきまでに叩きのめした。
人間の本性は「贈与」にある
レヴィ・ストロースは自身の研究の結果として全ての人間集団に共通する社会構造を発見した。
それは「男は、別の男から、その娘または姉妹を譲り受けるという形式でしか、女を手に入れることができない」ということである。
人間の作り出すすべての社会システムはそれが同一状態に止まらないように構造化されている。
そうなっている理由はおそらく、人間社会は同一状態にとどまっていると滅びてしまうからである。
構造主義四銃士その4。ラカンと分析的対話
ジャック・ラカンの専門は精神分析であり、「フロイトに還れ」という有名な言葉を残している。
本書ではラカンの思想のうち「鏡像段階」と「父—の—名」の2つに触れている。
鏡像段階とは人間の幼児が生後6ヶ月くらいになると、鏡に映った自分の像に興味を抱くようになり、やがて強い喜びの反応を示すようになる現象を指している。
この現象の原因についてラカンは、それまで自力で動き回ることも栄養補給することもできず、自分を取り巻く世界との「原初的不調和」の状態に置かれていた幼児が、鏡を通じて統一的な資格像としての「私」を獲得することによって「おお、これが<私>なのか」という深い安堵と喜悦の感情を経験するからだと述べている。
しかし、鏡に映った<私>は決して「私そのもの」ではないため、人間はこの過程において「私」の起源を「私ならざるもの」によって担保するという一種の狂気を抱え込むこととなる。
「エディプス」とは図式的に言えば、子供が言語を使用するようになること、母親との癒着を父親によって断ち切られることの二つを意味しており、ラカンはこれを「父の名」という言葉で語った。
混然とした世界に切れ目を入れて文節し、子供におのれの無力と無能を「説明」することが一つの父親の役割である。
人々がやくざや独裁者を恐れるのは、彼が「権力を持っているから」ではなく、独裁者がどんな基準で権力を行使するか予測できないからである。
(逆に権力はあってもそれを合理的なルールに則ってしか行使できない政治家や教師はそれほど恐れられることはない。)
大人になるということは、世界は私が生まれる前からすでに文節されており、言語を用いる限り、それに従う他ないという事実を自覚することである。
おわりに
本書で説明されている思想のなかには
すぐには飲み込めない難解なものも多く、
私の理解がどこまで完全なものかは少々怪しいところですが
少なくともソシュールやラカンなど今まで名前は聞いたことあるけれど
具体的にどんなことを語ったのかまでは知らなかった思想家について
その代表的な思想に触れることができたのはとても有意義な読書体験でした。
中でも今回初めて知った中で個人的に興味深かったのは
作者だけでなく、それを受け取る「読者」もまた
創造の参加者であるとするバルトの「作者の死」の概念ですね。
私は趣味で文章を書いた入り絵を描いたりしているので
こういう問題はとくに自分事として考えてしまいます。
また本書から得たものとしては
江戸時代の日本人の歩き方が今とは違っていたことや
北米大陸の先住民の贈り物合戦の文化(ポトラッチ)の存在などの
豆知識的な教養が増えたことも思わぬ収穫でした。
以上で本記事は終了となりますが
本書には今回取り上げなかった中にも
興味深い内容がまだまだ残されていますので
気になった方はぜひ一度手に取ってみてください。