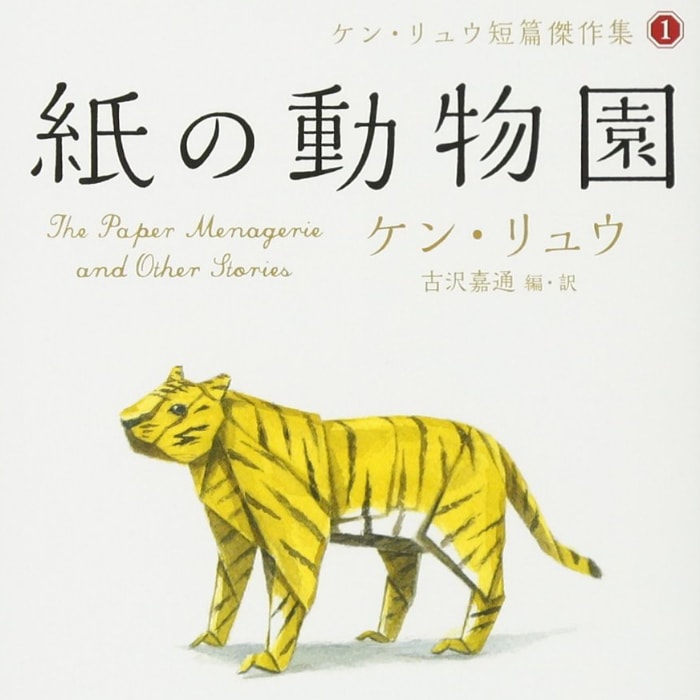まえがき
先週書店をぶらついていると、
優しいタッチのイラストの表紙に、
『又吉直樹さん推薦!』の
帯がつけられた『紙の動物園』という
一冊のSF短編集が私の目に留まった。

- 作者: ケンリュウ,伊藤彰剛,古沢嘉通
- 出版社/メーカー: 早川書房
- 発売日: 2017/04/06
- メディア: 文庫
- この商品を含むブログ (7件) を見る
SFにはあまり明るくない私だったが、
つい気になってパラパラとページをめくると
これがなかなかどうして面白く、
結局はこの本を買って
読むことになったのだった。
本作の著者は、中国系アメリカ人で
弁護士、プログラマー、作家という
三つの顔を持つケン・リュウ氏。
そんな著者が扱うのは、
言語、宇宙、AIといった自然科学、
そして、異なる文化に属する人間同士の
衝突や共生という、
まさにその経歴に相応しいテーマだ。
そこに、豊かな想像力と
最新の論文などから得たアイディア、
そして巧みな物語の
ディティールを付加することで、
本書は読み手をぐいぐい引き込む
上質なエンターテイメントに
仕上がっている。
しかしながら、私が読後
最も強く感じたことは、全編に
通底する身を切るような切なさだった。
どの物語も単純な
ハッピーエンドでは終わらない。
必ずどこかに、現実社会の
醜い部分が暗示されている。
それは時に目を覆いたくなるほど
残酷な形で提示され、
読み手は一話を読み終えるたびに
深く自問自答せずにはいられなくなる。
そして、今回私が本書を
こうして紹介したいと思った理由も
その強烈なメッセージ性に
強く心打たれたからだった。
さて、前置きが長くなったが、
ここからさらに本書に収録されている
一作づつに対してその感想を
述べていきたいと思う。
なんとか私なりに、
本書の魅力の一部でも
皆さんにお伝えできれば幸いだ。
※本稿には『紙の動物園』 のネタバレ要素が含まれます。
閲覧の際はその点をご了承ください。
紙の動物園 (The Paper Menagerie)
折り紙の動物を通して
異国人である「わたし」と
母の絆を描き、
ヒューゴー賞、ネビュラ賞、
世界幻想文学大賞など、
世界的の錚々たるアワードを
総なめにした表題作。
貧しい境遇から抜け出すため
自分を「紹介所」に載せ、
アメリカ人の「父」に買われて
渡米した香港人の「母」。
母国の文化を大事にする「母」は、
「わたし」に対し中国語で会話し
中国料理を食べさせるが、
「わたし」は成長するにつれ
アメリカ文化に馴染み、
そんな母を遠ざけるようになってしまう。
そして、母はやがて病気で亡くなり、
大人になった「わたし」は
かつて母が折ってくれた「老虎」の
折り紙を見つけ、そこに込められた
母の本当の想いを知ることになる…
というのが本作の大筋だ。
母と子のすれ違いというのは
古今東西ありふれた主題だが、
本作が傑出しているのは、そこへ
文化の壁と思春期の羞恥心という
センシティブな要素を絡めて、
一つの美しい物語にまとめ上げた点にある。
学校という
狭いコミュニティで生きる
思春期の子供にとって
「周りから浮く」ことは致命的なことだ。
(あなたは違っただろうか?
少なくともわたしはそうだった。)
だからこそ、異国の文化を捨てず、
周囲となじめない母を遠ざけた
「わたし」の気持ちが痛いほど分かるし、
また、そのことが読者が
「わたし」に自然と感情移入する
土壌作りにもなっている。
そして本作のラストシーン、
中国語で書かれた文章を
初対面の中国人女性に朗読してもらい、
(「わたし」はずっと中国語を避けていたので
母の字が読めなかったのだ…)
母の本当の想いを知った「わたし」が
ある行動をとった場面を読んだ時、
私の中に、胸が締め付けられるような
強い感情が湧き起こった。
「感動」という言葉は
今となってはテレビでもネットでも
だいぶ使い古された感があるが、
ここで感じた「感動」は
それらとは明らかに異質な
もっと強烈で根源的なもの
だったように思う。
数々の賞に選ばれたことも、
表題作に選ばれたことも
全て納得できる珠玉の一作。
初めて読むケン・リュウとしても
間違いのない作品だ。
月へ (To the moon)
ファンタジックなタイトルだが、
その内容は中国当局による弾圧と
難民の亡命という非常に
シリアスな問題を扱っている。
中国共産党から弾圧を受け、
亡命を希望する文朝とヴィニー父娘と
法が正義を実現すると固く信じる
新人弁護士のサリー。
サリーは何とかしてこの
「かわいそうな」父娘を
助けたいと思うが、
仕事を進めるにつれ、
自分の信じていた正義と
現実の埋めがたいギャップに
気づかされることになる。
現実に対するメタファーとして
嫦娥や孫悟空などが登場するなど、
ケン・リュウお得意の
幻想的な作風は健在だが、
作中に漂う空気は常に重く、
読後には何ともやりきれない気持ちが残る。
日本も全てが満足な国ではないが、
こうした世界の人々の現状を知ると
私たちはつくづく恵まれていると
改めて感じずにはいられない。
ちなみに、中国国内でも
人気のケン・リュウ作品だが、
この作品については
中国国内で一切の翻訳本が
流通していないらしい。
理由は…お察しである。
結縄 (Tying Knots)
アイディアの妙に唸らされた一作。
結縄文字(縄の結び目で
情報を記録する書記法)を現代に受け継ぐ
中国高地の少数民族の長ソエ=ボと、
その特殊な能力に目をつけた
アメリカ人のトムとの関わりを描いている。
そしてここからが凄いのだが、
トムの真の目的とは、
ソエ=ボの結縄文字の技術を利用して
量子物理学より難解な
タンパク質を正しく折りたたむための
正確で速いアルゴリズムを発見し、
それによって医療を発展させ
ついでに莫大な利益を得ることだったのだ。
古来の伝統技術が、最先端の
医療技術とつながるというアイディアには
思わず舌を巻いた。これは、
プログラマーとしての経歴も持つ
ケン・リュウだからこそできた発想だろう。
(ちなみに一見突飛なこのアイディアは、
科学雑誌ネイチャー誌の「マルチプレイヤー・
オンライン・ゲームでタンパク質構造を予測する」
という文献にヒントを得て生み出されたそうだ)
そして、ソエ=ボの協力で
医療が発展して万々歳…という風な
安易なハッピーエンドにしていない点も良い。
いつの時代も社会には強者と弱者が存在し、
強者は言葉巧みに弱者を言いくるめて、
気付いた時には何もかも奪い去ってしまう。
本作にはそうした
不平等に対する強い批判が
込められているようにも感じられた。
太平洋横断海底トンネル小史 (A Brief History of the Trans-Pacific Tunnel)
アジアと北アメリカを繋ぐ
海底トンネルが開通した
「もしも」の世界を、
トンネル開発に携わった
一人の労働者の視点で描いた作品。
一見荒唐無稽に思えるこの計画だが、
作中では、世界恐慌に対する
ケインズ理論に基づく解決策として、
日本の裕仁天皇がフーヴァー大統領に
話を持ちかけたことで
実現したと説明されている。
シアトルと東京が
海底トンネルで繋がったif世界を
疑似体験するような感覚も面白いが、
この作品における最も重要なテーマは
主人公チャーリーが最後にとった
ある行動に凝縮されている。
国家や権力に対する
個人の力は無力に等しいが、
ひとりひとりの勇気によって、
その後ろ暗い秘密を
隠しにくくすることは
できるかもしれない。
そんなかすかな希望を
抱かせてくれる一作だった。
心智五行 (The Five Elements of the Heart Mind)
宇宙で任務の最中に遭難した
女性飛行士のタイラが、
五行説に従い、原始的な生活を営む
オウタイ族の住む惑星に不時着し、
そこで青年ファーツォンと出会い、
彼らとともに生活する中で
人間的な生の喜びを取り戻すというお話。
この作品で面白かったのが、
人間の心と、人間の体内に棲む
バクテリアの関係性に注目していた点だ。
一般的にバクテリアというと、
食中毒や病気を引き起こす原因だと
捉えられがちだが、中には人間と共生し、
体内機能を助けているものもいる。
そしてさらに一部のバクテリアは
血流に化学物質を注ぎ込むことで
人間の気分や個性を変化させ、
つまり人間の心の働きすら
コントロールしているというのだ。
作中でオウタイ族の食物を食べて
バクテリアに「汚染」され、
しかし同時に自然で人間的な喜びを取り戻し
ファーツォンと恋に落ちるタイラ。
しかしタイラは、
ある出来事をきっかけに
再び体内のバクテリアを除去され、
今度は自分が冷たい機械に
戻ったような感覚に襲われる。
バクテリアが人間の心を変えるというのなら
自分自身の本当の心はどこに存在するというのか?
ファーツォンに対して感じていた感情は
自分のものだったのか、それとも
自分の中のバクテリアのものだったのか?
苦悩するタイラが選んだ最後の決断には、
もし自分がその立場なら、
どうしただろうかと強く考えさせられる。
ラブストーリのようであり、
哲学書のようでもある。
本作は私にとって特に
意義深い読書体験だった。
愛のアルゴリズム (The Algorithms for Love)
人間と見分けのつかない
高度なAIを搭載した
児童型ロボットの話は、
プログラマーでもある著者に
うってつけの題材だが、
作中には終始
物悲しい雰囲気が漂っている。
AIが生きてきている人間と
全く同じ人格を持てたとして、
果たしてそれが
私たちの愛する誰かの
代わりとなれるだろうか?
プログラマーなら誰でも
一度は考えるであろうこの問いに、
ケン・リュウ氏は
この作品でひとつの答えを
提示したように思える。
文字占い師 (The Literomancer)
「紙の動物園」の
最後を飾るのは、
本作で最も衝撃的で、
最も苦い読後感を残すであろう
この「文字占い師」だ。
主人公は、家族とテキサスから
香港に越してきて、
米軍基地内にある学校に通う
リリーという10歳の中国系の少女。
白人ばかりの学校で、リリーは
人種や中国料理のお弁当をダシにした
ひどいいじめを受けていた。
そんな中のある雨の日、
リリーは甘という老人と
陳という少年に出会い、
不思議な文字占いを教えてもらう…
というのが本作の導入である。
ここだけ読むと
いじめられていた少女が
新しい出会によって
いじめを乗り越える
ハートフルな物語に
思えるかもしれない。
しかし、本作の読後感は
ハートフルなどとは程遠い、
凄まじく重たいものだった。
その原因は、
この話の裏の主題である
二・二八事件に起因している。
(=1947年に起きた、
大陸側の支配に対する
台湾人の反乱)
この二・二八事件が
「文字占い師」の物語に深く絡みつき、
そして最終的に、ある衝撃的すぎる
展開を引き起こすことになる。
その詳細はここでは伏せるが、
例えるなら日本のテレビドラマでは
決して再現できないほどえげつない
結末だったというべきだろうか。
しかしながら私は、
ケン・リュウ氏があえて
この展開を選んだのには理由があり、
それは、安易な結末で
束の間読者を良い気分にするよりも、
時にあえて辛い選択肢を描くことで
作品の持つメッセージ性を
最大限に高めることだったのでは
なかったかと考えている。
そしてそうだとすれば
その試みは、確かに
成功したと言えるはずだ。
なぜなら、私を含む多くの読者の脳に
二・二八事件というワードとその意味が
忘れがたく刻み込まれたのだから。
おわりに
私が本書を読み終えて
強く感じたことは、
テクノロジーに対する盲信や
行き過ぎた全体主義への警鐘だった。
そして、久しぶりに
心から好きだと言える作家に
出会えたことを嬉しくも感じている。
読後感が少々重たいのが難点といえば難点だが、
手短に読める本格SF小説をお探しであれば
私は本書を強くオススメしたい。
私も、微力ではあるが
今後ともケン・リュウ氏の活躍に
熱い視線を送り続けたいと思う。